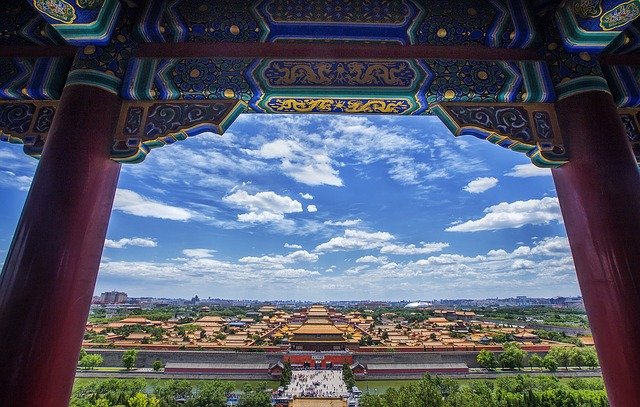生きとし生けるものすべてが決して逃れられないもの、それは「死」です。
人はなぜ生まれ、そして死んでいかなければならないのか。
その明確な理由はわかりません。命を得た者は、ただただ死という宿命を受け入れなければならないのです。
人類は現在にいたるまで、気の遠くなるような長い間、何度も何度も誕生と死を繰り返してきました。
それでも、なぜ生まれなぜ死ぬのか、という問いの答えは見つからないのです。
答えは文化や宗教、哲学によって無数に提示されています。しかし、どれが唯一の正解かを証明することはできません。
人間はどうあがいても死から逃れられません。これだけは確かです。
そして、いつか必ずやってくる死を恐れています。
はるか昔から人間は「死」について考えてきました。
では、古代人は「死」をどのようにみつめていたのでしょうか。

生と死の境目はどこにある?
そもそも、何をもって人の死とするのか、「死」を定義づけることは実はとても難しいのです。
文化によって死の定義は違いますし、時代によっても大きく変わります。
じつは現在の日本でも法律上、「死亡」について明確に定義づけられているわけではありません。

ベストセラー『バカの壁』などで知られる医学博士で解剖学者の養老孟司氏は、死について次のように言っています。
生死の境目というのがどこかにきちんとあると思われているかもしれません。そして医者ならばそれがわかるはずだと思われているかも知れません。しかし、この定義は非常に難しいのです。というのも、「生きている」という状態の定義が出来ないと、この境目も定義できません。嘘のように思われるかも知れませんが、その定義は実はきちんと出来ていない
生と死の堺目、つまり「人間が死んだ瞬間」は科学的に、はっきりわかっているわけではないのです。
ただ、一般的には3つの兆候をもって死亡したものとしています。
これを「三兆候説」といいますが、「呼吸の停止」「心臓の停止」「瞳孔拡散」の3つの兆候が確認できたときに人間は死亡したものとされます。

また脳の機能が完全に失われる「脳死」も人の死と判定されるようになりました。
死にはいくつもの段階がある
現代の私たちと同じように古代の人々も、生死の境目がどこにあるのかわかっていませんでした。
しかし、古代の人々は、生命が活動を停止してから、さまざまな段階をへて本当の死にいたるのだと考えていました。

古代人が「死ぬ」ということをどのように考えていたのか。
ヒントは「しぬ」という言葉そのものの中にあります。
「しぬ」は動物が生命活動を停止した状態をあらわす言葉です。これが植物の場合「しなゆ」という言葉に置き換えられます。
「しなゆ」は植物が萎れた状態をあらわします。
つまり人間が「しぬ」というのは、植物が「しなう」のと同じように、身体の水分が少なくなって萎れた状態になることなのです。
植物が萎れたからといって、完全に死んだわけではわりませんよね。あくまで水分が少なくなってぐったりしている状態です。まだ死にいたる最終段階ではないのです。鮮度が無くなり活き活きとしなくなった状態が「しぬ」なのです。
萎れただけなので、まだ生命はあります。

しかし萎れた植物をほっておいたらどうなるでしょう。
水分が完全に無くなって、「枯れて」しまいますね。
この「枯れた」段階が、本当の死なのです。

人間も「しぬ」状態から「かれる」状態になります。
「かれる」とは漢字で書くと「離れる」、古語では「離る」といいますが、これは魂が身体から抜けて、どこかへ離れて行ってしまった状態です。
古代人は、植物が萎れたように瑞々しさがなくなり(=しぬ)、やがて完全に水分がなくなり魂がどこかに離れていってしまった状態(=かれる、かる)、を完全な死、生命が失われた最終段階だと考えたのです。
草木が枯れたように、鮮度が失われ魂が抜けてしまった身体を「がら」と言います。漢字で書くと「骸」。
亡くなった人の残された体をあらわす「亡骸」という言葉は現在でもよく使いますね。
古代人は、身体から離れた魂は「根の国」へ行くと考えていました。
「根の国」は『古事記』にも出てくる死者の国です。

さて、魂が抜けた「がら」はどうするかというと、「ほうむる」ことになります。「ほうむる」は古語で「ほふる」、これは「放る」という意味もあるのですが、つまり亡骸を屋外に放置したのです。
「ほうむる」は漢字で「葬る」と書きますが、「葬」という字は草むらに死体を置く様子をあらわしています。
殯はなぜ行われたのか
古代、日本では天皇などの高貴な人が崩御したときには「殯」という葬送儀礼がおこなわれていました。
殯は、死者を埋葬するまで、遺体を棺におさめ、殯宮という死者の館を建てて、死者を慰める儀礼でした。復活を願う側面もあったようです。しかし、かなり長い期間おこなわれるため、遺体は腐ってしまい、白骨化しました。

殯とは、「本当の死」を確認するための葬送儀礼だったのです。
現代も殯の名残をとどめているものがあります。それが通夜です。
スサノオはなぜ髭と爪を切られ、天上界を追放されたのか
『古事記』に興味深いエピソードがあります。
スサノオが狼藉をはたらいたために、天上世界の高天原から追放されることになるのですが、このとき、スサノオは爪と髭を切られるのです。
なぜ爪と髭を切られたのでしょうか。
死を判定する条件として、「呼吸の停止」「心臓の停止」「瞳孔拡散」の3つをあげましたが、呼吸が停止して心臓がとまってたとしても、髭と爪は伸びます。
つまり死んでも伸びる髭や爪は生命力の象徴なのです。
生命力の象徴を切るということは、命を奪われることに等しいのです。
だからスサノオは見せしめに髭と爪を切られたのです。

約束をするときの「指切りげんまん」や、ヤクザの「指をつめる」も同じ意味があるといわれています。
指は命を象徴する部位であり、それを切り落とすことは命を差しだすことに等しいと考えられていました。
万葉集に詠まれた死
万葉集は奈良時代に成立したわが国最古の和歌集です。
全20巻4,500首以上の和歌が収められており、全体的に3つのジャンルに分類されています。
その3つとは、宴や旅のなかで歌われた「雑歌」、恋を歌った「相聞歌」、そして死に関する歌である「挽歌」です。
死も和歌を詠むうえで大きな一つのテーマだったのです。
いかに古代人が死について考えていたのかわかりますね。

最後に死をテーマにした「挽歌」のなかから、一つ紹介してこの記事を終えることにしましょう。
人はよし思ひ止むとも玉鬘影に見えつつ忘らえぬかも
巻二(一四九)(訳)他のひとは忘れ去ってしまうのかもしれませんが、わたしには美しい鬘のようにあなたの面影が浮かび続けて、どうしても忘れることができないのです。
※玉鬘は影にかかる枕詞。鬘とは、古代の髪飾り。つる草や草木の枝や花で作られた。
これは天智天皇が崩御したときに皇后である倭姫王(やまとひめのおおきみ)が詠んだ歌です。

その人の肉体は無くなっても、面影は思い出すことができる。思い出すことはできるが、その人はすでにいない。
でも死者を思うことで、死者は生き続ける。思う人のこころのなかで。実態は無くなっても、面影は誰かの心の中でずっと生き続けるのです。
だから残された人は、死者を忘れないために語り続ける。
死者のことを記憶にとどめ、語り継いでいく。
そうすることで、死者は永遠に生き続ける。
古人が心を込めて詠んだこの歌は、そう教えてくれているようです。